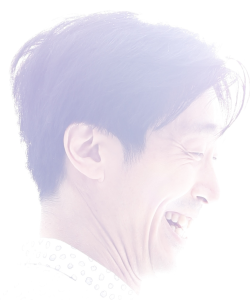
まずは動画組込ランディングページが、販促ツールの基本。そんな2022年夏。
今回はちょっと真面目な話をしちゃいます!

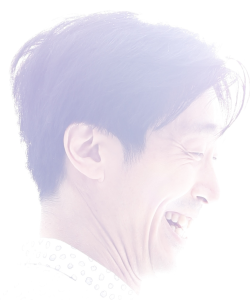
その前に、まず「通信」と「情報」について、
通信は電気、水道、ガスと同じ.ライフライン。
これまでは、通信といえば固定電話とFAXが主流だった。
しかし、アンテナ基地局や回線が整備されて携帯電話が個人に普及した。
また同時に、プロバイダーや回線が発達しインターネットも普及した。。
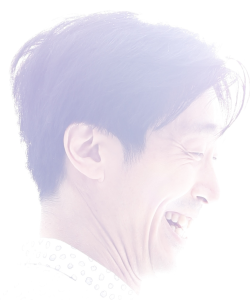
次に、「情報」は人、物、金に次ぐ第4の経営資源。
これまでは、情報といえば公的な文書を始め、書籍、新聞、雑誌など
紙媒体こそが信憑性のある情報源とされていた。
しかし、インターネットによる情報検索がパソコンやスマホで可能となり、
検索だけでなく、法人個人を問わず全世界に情報SNSで発信することができるまでにもなった。
むしろ、情報過多により取捨選択できるスキルが必要だよね。
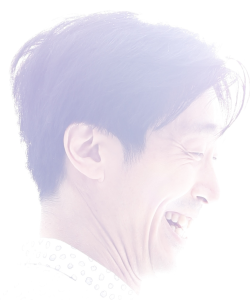
そして、対面よりもテレカンが主流になりつつあるこのご時世、
通信ができる環境で、情報を伝達することができる、
それがコミュニケーョン。
自分は現在50歳であるが、これまでに生きてきた時代とは、
世の中は変わったと思うので、根本からコミュニケーションとは何かを見直し、
いかに伝えたいコ卜を、コトバなのか、画なのか、音声なのかで、
それらを情報として人が頭で考える。
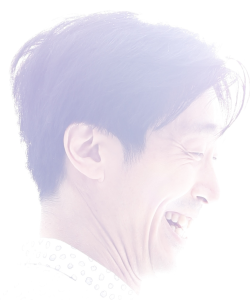
そして、昨今、働き方改革、DXというコトバが流行っているが、
よく理解も、実践もされていないと思われる。
それは、
データとかファイルとか、やはり紙媒体と違い目に見えない、
どこまでもカタチのないモノだからだと思われる。
デジタルにするとはどいうことなのか?
根本的な考え方も変える必要があると思う。
つまり、
これまで、人の力だけでやってきたコト(仕事など)を、
事務仕事もさらに機械化するということ。
工場にロボットを導入するのと同じである。
人がやることと機械がやることを分けて考えると理解しやすいかも。
人が集まり会社組織を構成しているが、
そこにさらに機械(サーバやパソコン、スマホ、ソフトウェア)を導入する。
事務的な業務を行う会社であれば、すでにパソコンは、
導入されていると思われるが、昔のワープロ的な考えで、
使っても、せいぜい、Word、Exel くらい。
文書の見栄えの問題で、あくまでも文書、紙をプリントする前提である。
と、表層部分で考えてしまうが、そうではなく根本から、
1)情 報:人が扱う
2)データ:機械が扱う
3)ファイル:人も機械も扱う
まず、これらのコトバを意識して使い分ける。
かつては人が紙に書いて残していた情報を、
現在では通信インフラに乗せられる
電子的情報つまりはデータ、にできるのか?
<ハードの環境整備>
データにするには、パソコンなどの機械や機械を動かす電気が要り、
<ソフトの環境整備>
さらにはそのパソコンやソフトウェアなど
機械を使うスキルが人になければならない。
そして、機械によって作成されるデータは、
文字や画像、映像、音声といった情報の種類によって、
人が作成し、保存して再現できるように分類されている。
それがファイルである。
ファイルにすると、紙で保存された情報よりも、
簡単に情報を再現できたり、共有が可能となる。
人が考え、伝え、保存したい情報を、
どれだけ多くの種類と量のファイルで作成し、
保存ができ、またそのファイルを再現できるのか
ということがスキルとなる。
これらファイルを人とコミニケーションをとりながら
作成する能力がビジネスには必要とされている。
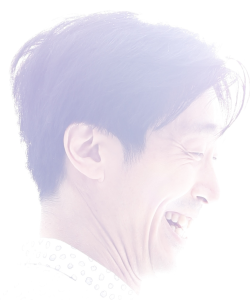
なかなか難しいが、
単純に考え、突き詰めれば、
伝える要素や手段とも重複するが、
情報のタイプは、それほど多くない。
【コトバ】
文字(言語違い有り)
#アルファベット26文字と
数字10文字は世界共通
→入力:キーボード、ペン、音声、タッチ
→出力:モニター画面
→出力:スピーカー
音声(言語違い有り)
→入力:マイク
→出力:スピーカー
【 画 】
画像(写真かイラスト)
映像(画像かイラストの連続)
→入力:カメラ、キーボード、ペン、タッチ
→出力:モニター画面
【 音声 】
人の声以外の音や楽曲
→入力:マイク
→出力:スピーカー
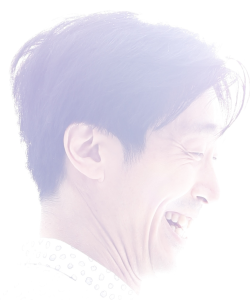
デジタルネイティブ世代は、
すべての情報は、
機械で動いているデータであり、
人が読みとれるファイルである。
と認識している。
アレクサで家電を操作し、
漢字をペンタブで練習し、
卒論をスマホで書き、
自身のファイルは、
クラウドにある。
スマホとネットがあれば、
生きていける世代。
パソコンやHDDは不用。
衣食住も
身軽なミニマリスト志向。
また、彼らにとって、
コトバと画と音声は、
すでに一体であり、
SNSが日々の日記帳。
この感覚のギャップを、
埋められるのか?
オタク気質とコミニケーション能力。
この相反する素養が必要とされていて、
これがこの業界で求められている素養なのかもしれません。